全国6ヵ所12公演で行なわれてきた『可憐なアイボリー全国ツアー2025 それは好きってこと』。そのファイナルの地は横浜ランドマークホール。
数年前、まだ“記念”の場として借りていたこの会場が、今や“締めくくり”として堂々使われるようになった。これだけで、彼女たちの歩んできた道のりがわかる。成長という言葉では足りない。これは、彼女たちと会場に足を運んだオーディエンスとの信頼の証明だ。
可憐なアイボリー。略してカレアイ。
その名がもう、少し特別な意味を帯びるようになってきた。
物語を“再現”するのではなく、“召喚”していた。
彼女たちのステージを観ていて、ふと浮かんだ言葉がある。
「カレアイは、アイドル界のストーリーテラーになれる」
ハニワことHoneyWorksの楽曲世界は、単なるJ-POPの枠を超えて、まるで短編映画のように構成されている。そこに必要なのは、歌唱力だけじゃない。演技力、存在感、そして何より“説得力”。
それを、今のカレアイは全部持っていた。
誰かの恋心、すれ違い、走り出す鼓動——。
そのすべてが、彼女たちの身体を通して再生される。
いや、違うな。再生じゃない。降霊。
HoneyWorksの物語が、彼女たちの手足を通して、声帯を通して、この世界に召喚されていた。
…イタコ?そう、イタコだ。
「可憐なアイボリーはアイドルシーンのイタコである。」
いかにも90年代の安っぽいバラエティ番組が付けそうなキャッチフレーズになってしまった。これならランドマークホールはさながらアイドルシーンの恐山になってしまうではないか(笑)
ま、そんな脱線はさておき…
感情の触媒としてのアイドル。
この表現力は、ひとつの完成されたフォームだ。
しかもそれは、誰かの模倣でもなければ、何かの延長線でもない。自分たちの中にいったん感情を通し、その体温で溶かしてから、観客の前に差し出すようなパフォーマンス。
可憐なアイボリーは、上質なメロディーと歌詞をソースに、「感情の触媒」としてのアイドル像を確立しつつある。
楽曲の中に眠っている感情と、観客の心の奥にある想いを化学反応させる——。そんな役割を彼女たちは担っている。
触媒は反応を促進するが、自身は変化しない。でもカレアイは違う。楽曲の感情を受け取り、自分たちも変化させながら、それを観客に届ける。まるで感情のエネルギーが彼女たちを通過する際に、より純度の高い形に昇華されるように。
それはもう、”歌って踊る”の先にある”伝える”の領域だった。
かわいい、だけじゃ済まない。
この日のステージで何度も思ったことがある。
この子たち、もう“かわいい”のステージにはいない。かわいいだけじゃだめな世界に歩みを進めた結果、「演じる力」が明確に宿っている。
それも、“わかりやすい演技”じゃない。本当にそこに歌詞の感情があると思わせるような、何色にもなれる透明な演技。
そしてなにより、メンバー一人ひとりが楽曲の物語に自分の“声”を重ねていた。
どこかで聴いた物語が、“今ここで”の実感をともなって眼前のステージ上で色彩を取り戻す。
物語の“続きを観たい”と思わせる力。
この日、何度も思ったのは“説得力”の質の違いだった。
あの子たちは、自分の言葉で、物語で、観客の中に感情の風景を作っていた。
それはもはや「いいライブだったね」じゃ終わらない。
ひとつの物語体験として、オーディエンス側の身体のどこかに残るものだった。
そして、いつの間にかそんなことができるようになっていた今のカレアイは、まだ少し戸惑いながらも、確かに風を受けて、次の物語へと帆を張っていた。
その歌と違うところがあるとするなら、甲板には彼女たちだけじゃないのかもしれない。この旅に、最初からついてきてくれた人も、途中から飛び乗った人も、一緒に立っているのかもしれない。
そんな風景の続きを、そんな物語の続きを観ていたい。帆に受ける風を感じながら。
というツアーファイナルだった。
…ていうか、待て待て。知らないうちに可憐なアイボリーがすごいグループになってたんだけど。
え、どうした?何が起きた? 君らいつも、もっとこう、ふにゃふにゃのヘラヘラな感じですやん。
ふーむ。これが「ギャップにやられた。」というやつか!
(お疲れさまでした。)
/
— 可憐なアイボリー (@Karennaivory) May 25, 2025
4周年記念LIVE開催決定!🎉#可憐なアイボリー 4th Anniversary Live
\
🗓️10/5(日)
📍Spotify O-WEST
新たなページがめくられる、
可憐なアイボリーの物語
僕が歩く今日が続きだ#カレアイ pic.twitter.com/hUmYuqG4PO
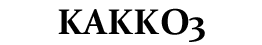



コメント