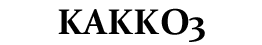Takui Nakajima held a live tour for the 20th anniversary of his debut. In Tokyo, the gig was held in LIQUIDROOM at Ebisu on March 6th.
In recent years, he has written songs for some groups of Hello! project. The project includes C-ute, ANGERME, and Juice=Juice.
In the gig, he played many songs includes his songs for them, for example “Taiki Bansei” by ANGERME.
中島卓偉の20周年を記念したツアー『TAKUI NAKAJIMA LIVE TOUR 2019 20th ANNIVERSARY REQUEST OF BEST SEASON2』が、3月9日、恵比寿リキッドルームにて行なわれた。
今回のツアーは、ファンから事前に聴きたい曲のリクエストを募って、得票数の多い曲を演るというコンセプトのもの。15周年の時に取り入れた“ライブで聴きたい卓偉曲”を堪能できるこの形式を、デビュー20周年の今回も実施することで、ファンへの感謝の気持ちを表したものになっていた。
初日のHEAVEN’S ROCK さいたま新都心に続き、3月27日にリリースされるセルフカバーアルバム『GIRLS LOOK AHEAD』からの楽曲がBGMとして流される開演前。そして、詰めかけた900人以上のオーディエンスの熱量が立ち込める中で、いよいよ開演の時を迎える。ギター・生熊耕治、ドラム・安東祐介、ベース・鈴木賢二のいつもの面々がステージインしたのち、片手を上げて中島卓偉がステージへ。「歌うぜ東京ー!」と卓偉はシャウトを一発決めて、大歓声に迎え入れられての1曲目は「蜃気楼」。煌々と照らされたステージ上、ツアービジュアルと同じ真紅のジャケットにドレスシャツで卓偉が歌えば、フロアからはいくつもの拳が突き上げられて、興奮と熱量が沸き立つ森を形成する。そんな光景を目にして、卓偉も相変わらず絶好調。牙を剥くかのようなシャウトを連発してオーディエンスをこれでもかと煽りまくっては、ステージを所狭しと動き回る。
「時間を1999年に戻します! 中島卓偉のデビューシングル行きます!」と、言葉を放って、スティミュラスな赤いライトと素肌を突き刺すようなスリリングなサウンドに会場が染め上げられる「トライアングル」。次々に撃ち込まれるメロディアスなパンクロックの数々に、オーディエンスも冒頭から歓喜の声を上げっぱなし。フロアを揺らすコールと大合唱、そして拍手喝采の波が幾重にも重なって、これはライブ序盤なのか、それとももう後半なのか、時間も空間も超越した、もしくは麻痺してしまったかのような感覚へと誘われる。
抱えたGibson SG Juniorのチューニングが合ってないというトラブルもあった「HELLO MY FRIENDS」では、卓偉の声がかき消されるほどの大合唱とコール・アンド・レスポンスが会場全体を包み込む。その辺のライブイベントでは決して味わうことができない、強烈なほどの一体感。これには卓偉も嬉しそうな笑顔を見せる。
「今日はリクエストライブということでね、先に言っとかなきゃいけないのは、申し訳ないのは、“リクエストライブ”って、知ってる曲が3曲くらいある人がやるライブなのね。俺、20年1曲も売れてないから。今日初めてライブ観るって人もいるかもしれないけど、基本、知ってるのお前らだけっていう。初めて観る人からすると、1曲も知ってる曲がないってライブだから。しかもリクエストしてくれたTOP30をバーっとやるんだけど、自分が好きな曲は10曲くらいしかなかった。そういう残念な思いもありながら、今日はお前らのためだけにやるから!」
「一曲も売れてない曲で遊ぼうぜ!」と、いつもの自虐気味なMCから突入した「カモン!カモン!」では誰もが頭の上でクラップ。曲が売れる売れないは、いわば運とタイミング。プロモーション力や予算投入でハンドリングもできたが、そんなものは過去の話。マスを含めたメディアが自滅的に信頼度を低下させ、一方で趣味嗜好の多様性、細分化された現在。国民的ヒットなんてものは、おいそれとは生まれない。しかし同時に、卓偉の曲を、卓偉の歌を全身で楽しみ、熱狂し、声を上げ、拳を振り上げる900人の姿を見ていると、売れる売れないと作品の評価は関係ないことを思い知らされる。“紙切れのおまけ”として大量生産大量消費される曲では、これだけの人たちの心を引きつけ、動かすだけの一体感は生み出せない。
カッティングギターが心地よいスカアレンジの「大器晩成」(言わずと知れた、アンジュルム提供曲)でフロアを踊らせると、「続けろ」の脈拍が早くなるようなドラムのイントロがフロアの熱気を一気に高める。なぜか「恵比寿!」のコールも飛び出す“めっちゃストロング”な遊び心で、拳を突き上げるオーディエンスのボルテージは限界突破の狂喜乱舞。そのまま「YES. MY WAY」へとなだれ込めば、卓偉が紡いだ熱いメッセージのロックンロールに誰もが陶酔し、声が続く限り歌い叫ぶ。卓偉もその気持ち応えるようにステージを動き回り、言葉に感情を詰めて幾度となく歌を撃ち放つ。
“ストロベリーフィールズ”を想起するトラックに卓偉のブルースハープが重なる「さらば摩天楼のFairy Tale」。全身全霊で熱唱する卓偉の後ろに陽炎のように見えたのは、卓偉が歩んできた20年の幻か。ただただロックに、自分の音楽を信じて歌い続けてきた男のシルエットが、ステージに揺れていた。
「UP TO DATE」から始まり、「BE MY BABE?」「FREE FOR FREE」がパンキッシュに続けば、フロアは飛んで跳ねての大騒ぎ。「歌って!絶対に!すべて上手くいくから!」と、卓偉がステージから檄を飛ばした「どんなことがあっても」では、「どんなことがあっても 決して諦めたりしないで」とひとりひとりが自らを鼓舞するようなシンガロングがいつまでも続いた。
「TO THE MAX」「我が子に捧げる PUNK SONG」など、卓偉のロックに煽られてパンパンに膨れ上がった熱気を含んだ会場は、ライブ後半になってもなお、サッカーのアンセムのような強烈な一体感を保ったまま推移をみせる。
テレキャスターに持ち替えて、ギターのアルペジオで構築された幻想的なイントロからの「テルミー東京」。上京したばかりの卓偉の想いが綴られたこの曲が歌われるたび、我々は思う。都会の片隅で取り残された気持ちになっても、卓偉の歌はいつもそばにいてくれた、と。夕焼けのように染まるステージで、卓偉が歌い続けるかぎり、卓偉の歌はこれからもそばにいてくれる。卓偉もそれを知っているからこそ、歌い続けた20年。「リクエストライブなのに自分が好きな曲は10曲しかなかった! 20年経ってもお前らとは分かり合えないことを実感してます。」と、今日も笑いをとる発言を繰り出していたが、分かる分からないよりも深い場所で、卓偉と我々は繋がっているのだ、と。
「Calling You」から始まる後半戦は、リクエストのTOP10に入っていた曲ばかりということで、もちろん一曲ごとにみんなでハンズアップでの大合唱。ステージの卓偉を輝かせるライトの照り返しでオーディエンスの影が浮かぶ。卓偉のライブは、客席側までが暗くなることはあまりない。それは観客も含めての中島卓偉のライブであり、観客こそが中島卓偉のライブを完成させるための最後の1ピースだから。そして思い浮かぶ光景はいつも、卓偉を求めるいくつもの腕の向こう側で、コントラスト強めの光を浴びて、汗を滴らせ、力を振り絞って、喉がかき切れんばかりの熱唱を続ける卓偉の姿。
この完璧なまでの空間に、我々はただ魅せられて、また心を奪われる。
「東京、歌声を聞かせてください!」とシャウトを繰り返す卓偉。「ピアス」をドラマティックに披露して、中島卓偉のバラードのひとつの頂点、ツアーのためにアレンジされた「3号線」のコール・アンド・レスポンスへ。歌に描かれた当時の卓偉少年の気持ちを、卓偉はステージ上で演じるように歌い上げる。誰もがその姿に引き込まれて、いつの間にか歌詞を口ずさむ。その後の親子関係は卓偉のタトゥーの話とともに聴いたことがあったとしても、「3号線」を耳にするこの瞬間、卓偉少年が見た当時の光景と感情は鮮やかに再生され、エモーショナルなステージに目元を拭う観客もいた。
スリリングある疾走感。攻撃的なサウンドにかかってこいと言わんばかりの卓偉のボーカルで披露される「イノヴェイター」。フロアの熱量は四方八方で暴発を繰り返す。それはシャウトとシャウトのぶつかり合い、ロックの衝動と狂乱が混じり合って、はてしない興奮がフロアを満たした。
「本当に集まってくれてどうもありがとう。20周年だからといって、これといったことが何もできず、アルバムはいいタイミングでリリースできますけど、20年ついてきてくれている人もたくさんいるのに、何も新しい景色を見せることができず、本当に申し訳ないと思っています。この先も、いろんな大変なことがあるかもしれないし、難しくなることもたくさんあるかもしれない。だけど、ひとつひとつを楽しんでいかないと、乗り越えていけないという気持ちもあるし、アーティストとバンドと、オーディエンスの関係っていうのは、お互いが必要とする限り、いつまでも続いていくものだと思います。」
最後のMCで、卓偉はそう言ってオーディエンスに頭を下げる。では、卓偉が今日、我々に見せてくれた景色は、いつも見慣れたつまらない景色だったのか? いや、それは違う。卓偉が見せてくれたのは、この日、この場に集まった人たちにとって、何よりも大切で、尊く、熱く、やさしく、温かい景色。
新しい景色よりも大切にしたい景色。
中島卓偉がこれまで見せてくれた景色、そしてこれからも見せてくれる景色は、我々がいつ、誰にでも胸を張って自慢できる、そんな景色ばかりだ。